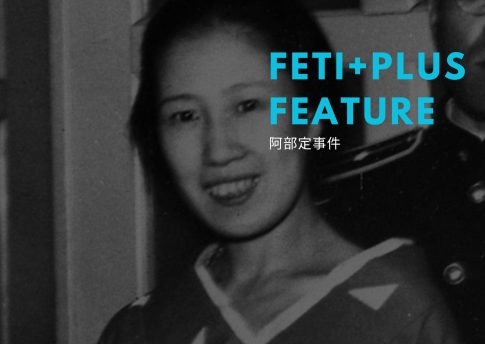羽田圭介がSMを“文学”にした一冊『メタモルフォシス』
小説家・羽田圭介のSM小説集『メタモルフォシス』(新潮文庫)は、
中編2本「メタモルフォシス」「トーキョーの調教」を収録した、SMとマゾヒズムを真面目に文学化した一冊です。
昼は「きちんとした社会人」として生きる男たちが、夜になるとSMクラブや調教の場で“奴隷(M)”として振る舞う――という設定だけ聞くと、エロ寄りのSM小説を想像しがちですが、羽田圭介はそこを徹底的に“文学”として書き切っているのが特徴です。
- SMプレイそのものよりも、
- なぜ人は痛みや支配を求めるのかという心の動き
- 「社会的に正しい自分」と「本能的な欲望としての自分」のズレ
- 奴隷であるときにこそ浮かびあがるアイデンティティ
といったテーマを、純文学の筆致で掘り下げていきます。
さらに面白いのは、「トーキョーの調教」が、羽田圭介本人いわく「一番、芥川賞を狙って書いた作品」だというエピソード。インタビューで本人が、
「もう芥川賞を目指すしかないか、と思って書いたのが『トーキョーの調教』というSM小説」「執筆・直しを含めて2年くらいかけて書いた」
と語っており、賞レースを本気で意識しながら練り上げられたSM小説であることがわかります。
結果として、単行本化の際に“抱き合わせ”で書いたもう一つのSM小説「メタモルフォシス」の方が芥川賞候補になった、という皮肉な経緯も含めて、「羽田圭介×SM×純文学」という文脈で読んでほしい一冊です。
第1作目「メタモルフォシス」──証券マンが“奴隷”になるまで(ネタバレなし)
1本目の「メタモルフォシス」は、
証券会社で働くエリート営業マンが主人公のSM小説です。
高齢者相手に金融商品を売り込む、成果主義の世界で生きる彼は、
・スーツを着ているときは、どこから見ても「優秀な会社員」。
・しかし仕事を離れると、SMクラブに通い、女王様の前でひざまずく“奴隷”としての顔を持つ。
物語は、この二重生活が少しずつ「奴隷側」に傾いていく過程を追いかけます。
より強い刺激を求めていくうちに、プレイはどんどん先鋭化していき、彼は「完全に支配される」状態の中でしか見えない景色を求めるようになっていきます。
ここで羽田圭介が上手いのは、SMを単なるセンセーショナルなネタにせず、
- なぜ彼は、仕事では「合理的」でありながら、
- SMの場では「非合理」に見える快楽を追い求めるのか
- その矛盾のなかで、彼の価値観や生き方がどう変容(メタモルフォシス)していくのか
を、コツコツと言語化していくところです。
痛みや屈辱を求める自分を“変態”として切り捨てるのではなく、
「そこにこそ自分の核があるのでは?」と真面目に考えてしまう主人公の姿が、
このSM小説を、ただのエロではない“文学作品”に押し上げています。
結末で彼が何を「見出す」のかは、ぜひ本編で確かめてほしいところです。「快楽」と「自分」を見出すのか――そこは、ぜひ本編で味わってください。

第2作目「トーキョーの調教」──講師と生徒、奴隷と女王様(ネタバレなし)
2本目の「トーキョーの調教」は、
東京のテレビ局に勤めるベテラン男性アナウンサー・カトウが主人公のSM小説です。
家庭も仕事も“きちんとしている”彼は、軽い興味からM調教に通い始めます。
最初は素人のMとして、恐る恐るSMの世界に足を踏み入れるのですが、
調教を重ねるうちに、彼のMとしての覚醒と成長が加速していく。
いつも指名しているSMクラブの女王様・マナが、
実は自分が講師を務めるアナウンススクールの生徒でもある――。
ここから、
- 昼:アナウンススクールで 「講師」と「生徒」
- 夜:SMの場で 「奴隷」と「女王様」
という、公私で立場が完全に逆転する関係が始まります。
この設定だけ聞くとかなりフェティッシュですが、羽田圭介はここでもSMを真面目に扱います。
- 言葉を商売道具にするアナウンサーという職業と、
- 言葉ひとつで相手を縛り、解放する女王様との関係、
- 仕事の倫理観と、Mとしての欲望のあいだで揺れる主人公の内面
など、「調教」を通じて人間関係と自己認識が変容していくプロセスが丁寧に描かれています。
「トーキョーの調教」は、SMプレイのディテールよりも、
- “見られる側”のアナウンサーが、
- “見下され、命じられる側”の奴隷として快楽を見出していくこと
- そして、その変化が仕事や家庭にもじわじわ影響していくこと
を通じて、「自分にとっての正しさ」や「自分らしさ」とは何かを問うSM小説です。
SMをネタ的に消費するのではなく、
「SMという極端な状況を使って、人間の欲望とアイデンティティを描く文学」として読みたい人には、
『メタモルフォシス』はかなり刺さる一冊だと思います。