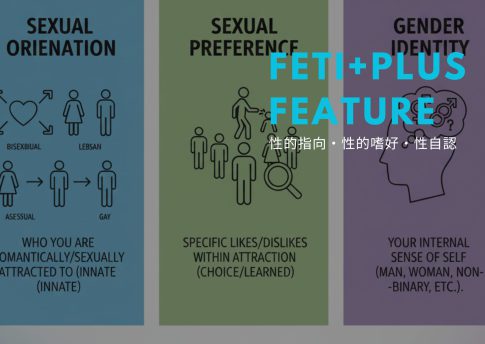ヨーロッパに存在した “死後写真” ― 愛する人を残すための最後のポートレート
19世紀のヨーロッパには、亡くなった人の姿をそっと写真に収める「死後写真」という文化が存在した。いまの私たちからすると奇異にも映るが、当時の人々にとってその一枚は、愛する人を永遠に残すためのごく自然な行為だった。写真がまだ高価で特別な技術だった時代、生前に写真を持つことができないまま別れが訪れる家庭は多く、死後写真は“最初で最後のポートレート”となることが多かったのである。さらに、キリスト教文化における「死は旅立ちである」という思想も影響し、安らかな姿を残すことは家族にとって慰めとなった。

“生きていた姿”を再現するための工夫
死後写真の特徴のひとつは、亡き人をあたかも生きているかのように表現しようとした点にある。遺体を椅子に座らせたり、ベッドに寝かせたりして、静かに眠りについているように演出する方法が一般的だった。特に幼い子どもの場合は、親が抱きかかえたまま撮影されることもあり、写真には深い愛情と悲しみが同時に写り込んでいる。また、初期の作品では、閉じた瞳の上に瞳を描き足して“目を開けているように見せる”など、写真的な加工が加えられることもあった。白い花や十字架を添える演出も多く、死後写真は単なる記録ではなく、亡き人を美しく敬いたいという家族の願いそのものだった。





消えていった文化と、写真に残された永遠
20世紀に入ると、死後写真は急速に姿を消していく。写真が安価になり、生前の姿を簡単に残せるようになったこと、そして医学の発展で死亡率が下がり、死が日常から遠ざかったことが背景にある。また、社会の価値観も変化し、死を直接扱うことが次第にタブー視されるようになった。しかし残された死後写真を見つめると、そこには“忘れたくない”という切実な感情が静かに宿っている。死後写真は、19世紀の人々が死と向き合い、限られた手段の中で愛をかたちにしようとした証である。その一枚一枚は、時代を超えて、誰かを想う気持ちの普遍性をそっと語りかけてくれる。